去る8月12日、金剛寺の「施餓鬼会」を厳修しました。



当日、参列者の皆様にお話ししたことを簡単に紹介したいと思います。
「施餓鬼会とは何なのかは、様々な本やHP等で調べることが出来ますが、私の施餓鬼観は次の3つの視点があると考えています。
①仏教の六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)は、ヒンドゥー教の輪廻転生の考えを受け入れた形で成立。日本の古神道と融合して、餓鬼道で苦しむ霊に食事を施すことで先祖、新仏の追善供養になると、全国的に各宗派(浄土真宗を除く)の寺院でお盆の時期に盛んに行われるようになった。
②始まりの時期は、鎌倉時代。
定着したのは、江戸時代。
なぜ、宗派にかかわらず全国の村々に定着したのか?
それは、全国の村々の神社の祭りが定着したことと深くつながっていると私は考えている。
つまり、5世紀に大陸から伝わった疫病が猛威をふるいパンデミックが発生、免疫の無かった多くの人々が感染死した。
平安時代以降、朝廷からその対処として神社に求められたのが穢れ(鬼)を払う大祓。
寺院に求められたのが鬼を鎮める施餓鬼会(他に大般若経、造仏など)。
江戸時代に入り人々に一定の免疫が定着。パンデミックが減少したのは、村祭りや施餓鬼会のお陰だと医学や科学の未熟だった当時の人々は考えた。
そして、施餓鬼会に参列し、疫病を伝染させる鬼に施すことで「自分には疫病を感染させないで下さい」と現世利益(げんせりやく)を願ったのが全国的に定着した大きな要因だろうと考えている。
③もう一つ、現代的な科学や生物学からの視点があることも忘れてはならない。

それは、この施餓鬼棚にお祀りする位牌。『三界萬霊 十方至聖』(さんがいばんれい じっぽうしいしん)と刻まれている。
この世界の生きとし生けるもの全ては、(様々な命を頂いて生きている。無駄な命は一つもない、全てがお互いがお互いを支え合っている。)それぞれが成仏する。(するべきである)
人間は、こうした食物連鎖のおかげで生きている。今自分は、こうした全ての命によって生かされていることに感謝し、全ての命を供養するのも大きな目的のひとつである。
施餓鬼会には、この様に様々な歴史と背景が有ることを知って頂ければ幸いです。」

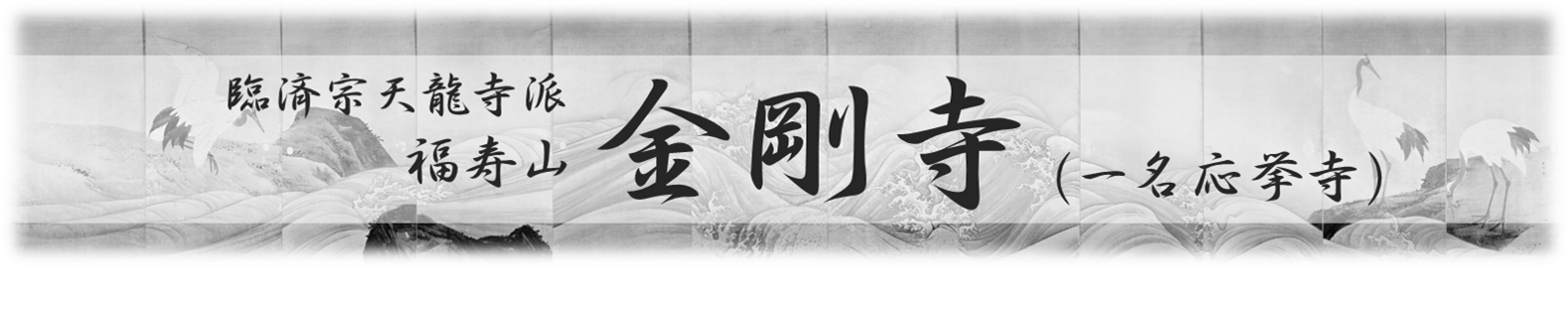

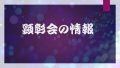

コメント